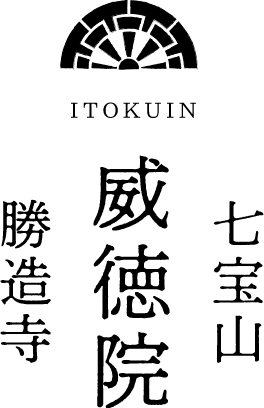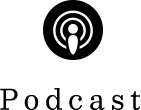8月法話「盂蘭盆(うらぼん)」
香川県では8月がひと月遅れのお盆です。お盆は「盂蘭盆(うらぼん)」の略称で、インドの言葉である梵語ウランバナの音訳です。その意味は「救倒懸(くとうけん)」(逆さまに吊るされるような餓鬼道の苦しみから救う)ということです。
お釈迦さまの弟子に目連という神通力に優れた人がいました。ある時、神通力で亡き母の死後の様子を見ると、地獄道に堕ちて飢餓(がき)の苦しみを受けて骨と皮とに痩せ衰えていました。そこで目連は、食器にご飯を盛り差し上げると喜んで食べようとしますが、ご飯が焔となって食べることができず、返って母の苦しみは増すばかりでした。この様子をお釈迦さまにお話しすると、「目連よ、汝の母は罪障が深いためにその報いを受けているので、汝一人の微力ではどうすることも出来ません。7月15日の衆僧自恣(じし=自己反省)の日に百味の飲食や五果を十方の衆僧や大徳に接待供養しなさい。そうすれば母の罪障は消滅し、苦しみの世界から脱して安楽の世界に生まれるだけでなく、現世には寿命長久、来世には楽土に往生することが出来る」と諭されました。
そこで目連はお釈迦さまの教えの通りに7月15日に衆僧に百味五菓を供養して母の解脱を願ったところ、母は餓鬼道の苦しみからの脱(のが)れることができたのです。亡くなった人びとを餓鬼道の苦しみから救うために始まったのが、こ盂蘭盆の起源です。
いつの頃からかこの「盂蘭盆」の同音語である「裏盆」の言葉が現れ、地蔵盆のことを「裏盆」と呼ぶようになってきました。しかし、あくまでも仏教に「裏盆」という言葉はありませんし、 「表盆」もありません。